「うちの子、国語が苦手で…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
・読解問題を嫌がる
・漢字を覚えたがらない
・本を開こうともしない
それらの様子に、「苦手なんだな」「やる気がないのかな」と心配や焦りを感じる親御さんは少なくありません。でも、子どもたちの反応の奥には、もっと別の“理由”が隠れているかもしれないのです。
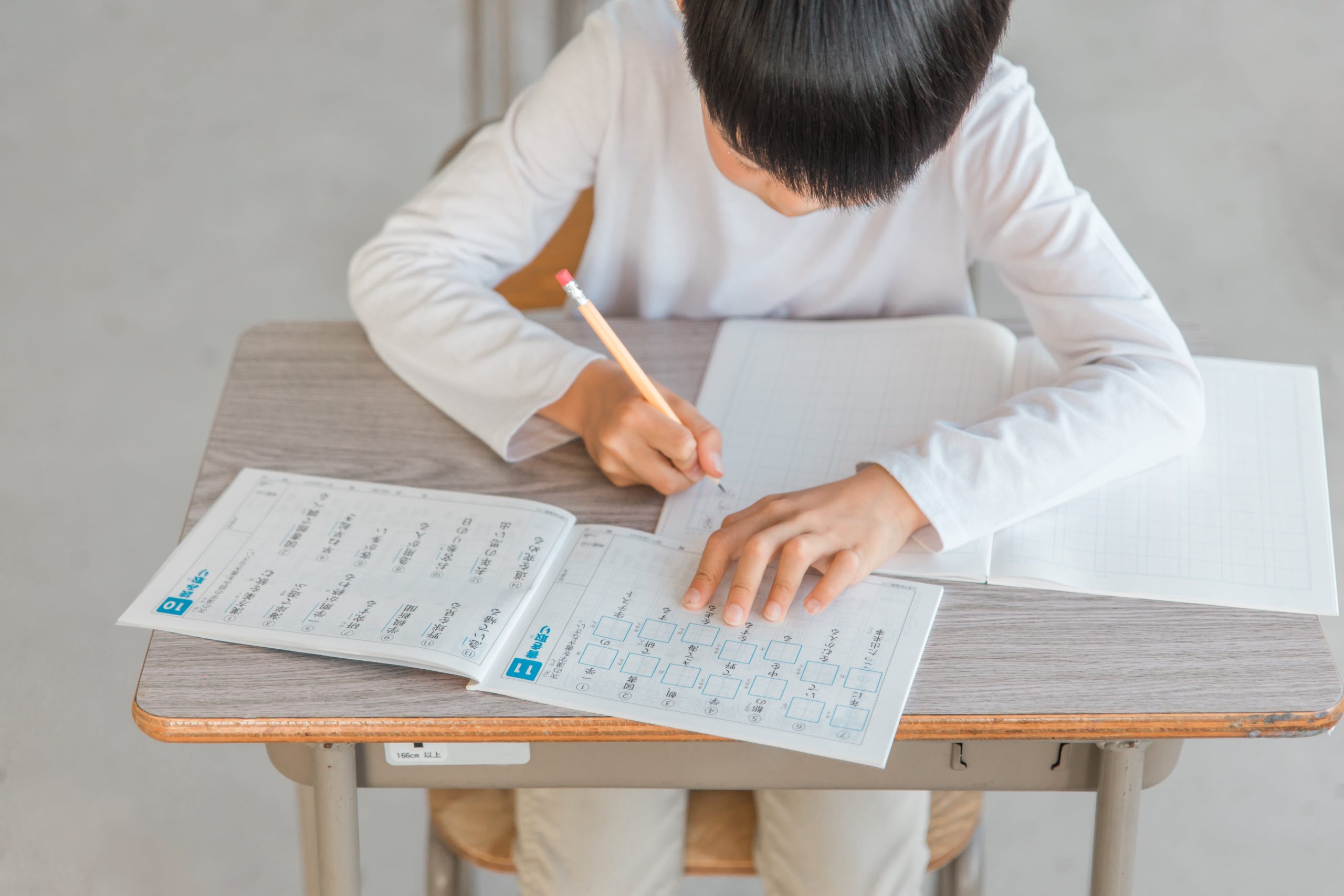
「うちの子、国語が苦手で…」
そんなふうに感じたことはありませんか?
・読解問題を嫌がる
・漢字を覚えたがらない
・本を開こうともしない
それらの様子に、「苦手なんだな」「やる気がないのかな」と心配や焦りを感じる親御さんは少なくありません。でも、子どもたちの反応の奥には、もっと別の“理由”が隠れているかもしれないのです。

教育家・見守る子育て研究所 所長
1973年生まれ。京都大学法学部卒業。
私は学生時代から大手受験予備校、大手進学塾で看板講師として学習産業に関わってきました。
大学を卒業した後、ご縁をいただいて、社会人プロ講師によるコーチング主体の中学受験専門個別指導塾を創設し、以降18年間に渡って代表を務めてきました。
「国語が苦手」「文章が嫌い」——
この言葉、実は子ども自身が初めに口にしているケースは少ないようです。多くは、宿題の取り組み方やテストの点数、読み聞かせへの反応など、大人の視点から「これは苦手なんだろうな」と判断された結果、子どもに“苦手”というレッテルが貼られてしまうのです。
たとえば、漢字の宿題をいやがる。
読み聞かせ中に目をそらす。
音読がなかなかスムーズにできない。
その場面だけを見て「この子は国語が苦手」と思ってしまう。でも、本当にそうなのでしょうか?
子どもにはそれぞれ、生まれ持った才能の傾向——「才能タイプ」があります。
たとえば、体を動かすのが大好きで、遊びながら学ぶのが得意な子。あるいは、目で見て全体を捉え、結論に素早くたどり着きたいタイプの子。
そんな子に、黙って机に向かって文章を読むことを求めたり、同じ漢字を10回ずつ書く反復練習を強いたら…どう感じるでしょうか?
「つまらない」「終わりが見えない」「なんでこれをやるの?」
そう思ってしまっても、無理はありません。
子どもが持つ“理解のしかた”や“刺激への反応の仕方”に合っていないやり方を続ければ、どんなに能力のある子でも、やる気はしぼんでしまいます。結果的に「国語が苦手」「文章が嫌い」と思い込んでしまうのです。
あるお子さんのケース。
もともと本が好きだったのに、あるときからまったく読まなくなった。理由をたどってみると、お父さんが「読ませたい」と買い与えた難しめの全集がきっかけでした。
字が小さく行間も狭い本。ぱっと見て「重い」と感じる子どもにとって、その1冊がプレッシャーになってしまったのです。
そこで行ったのは、拡大コピー。
面積が2倍になるように文字を大きくして、見開きを半分に分けて渡してみると…なんと、読んだのです。目で捉えやすくなるだけで、「読みたい」という気持ちが戻ってきました。
読む力がなかったわけではありません。
“合う形”で渡されなかっただけだったのです。
私たち大人も、実はそれぞれ読み方にクセがあります。
・目的がはっきりしていると読めるタイプ
・感情移入しながら読み進めるタイプ
・オーディオブックのように、音声で聞いてから内容を理解するタイプ
子どもも同じように、視覚・聴覚・身体感覚のどこをよく使うかによって、読みやすさが変わります。なのに「自分がやってきたやり方」「先生が正しいという方法」だけで進めようとすると、ミスマッチが起きてしまいます。
まずは次の3つを意識してみてください。
① 苦手な場面を観察する
どんな時に「読まない」「やりたがらない」のでしょうか?
姿勢? 時間帯? 声かけの仕方?
その場面を具体的に振り返ることで、きっかけが見えてきます。
② 子どもの才能タイプの傾向を見立ててみる
・体を動かしながらなら聞ける
・図鑑や映像コンテンツは集中して見られる
・自分のタイミングで黙々とやりたがる
そんな日常の“好き”や“得意”をヒントにして、「どういう刺激に反応しやすいか」を探してみましょう。
③ 伝え方・渡し方をカスタマイズする
・読み始めは1ページではなく2行だけ
・文字を大きく・少なくして渡す
・本人のペースを待ち、話しかけすぎない
・一緒に読み始めて、途中で任せてみる
本人の「読めた」「できた」という体験を積み重ねることで、「自分にもできる」「読んでみたい」につながっていきます。
子どもが国語や漢字を嫌がるとき、それは“本人の力不足”ではなく、
ただ“合ってないやり方”を押しつけられた経験の積み重ねかもしれません。
無理をさせる前に、
「この子にとってのやりやすさってなんだろう?」
「どうすれば、この子が気持ちよく読み始められるかな?」
そんな視点で一歩立ち止まって考えてみてください。
お子さんの中にも、きっと“読めているもの”があるはずです。
ゲームの攻略本かもしれません。
好きなYouTubeのコメント欄かもしれません。
それをきっかけに、「この子はこういう形なら読めるんだ」と知るだけでも、親子のコミュニケーションは大きく変わります。
そして何より、親自身も「読むってどうしていたっけ?」と自分を振り返ってみることがヒントになります。
お子さんの「できる」を引き出すのは、知識ではなく“理解”と“観察”から。
子ども本来の力を信じて、まずは今日の読み方を少し変えてみませんか?